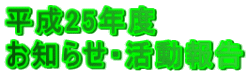
今年も残すところ、あとわずかとなりました。この一年、海藻農法普及協議会主催の野菜市やセミナーなど
でスタートし、アマモ場が消えそうになったり、泳がいやの開催を見合わせたりと心配することもありました。
夏以降は、関西国際大学のインターンシップ実習生が再び中海を訪れ、その明るさに救われる思いでした。
秋には、今年から中海の海藻肥料を使って栽培したお米が高く評価されるなど嬉しい知らせもありました。
天候などの理由により開催を延期したアマモ移植イベントでは、新しい出会いもあったりと実り多き一年に
なったと思います。
お忙しい時間を調整して、イベントに参加してくださった皆さんや多くの方のご協力・お力添えにより、無事
今年一年を終えることが出来ました。大変お世話になり、本当にありがとうございました。
(平成25年12月5日更新)
平成25年11月に発行された中海エコ活動レポート第13号に海藻採取による浄化活動を学ぶため、関西
国際大学インターンシップ実習生が中海を訪れた時の記事が掲載されました。
「中海エコ活動レポート」第13号はこちらから
鳥取・島根両県のNPO、行政機関等の中海の環境改善、賢明利用に関する取組みが取り上げられてい
ます。鳥取県のHPよりご覧いただけますので、中海に興味のお持ちの方はぜひ読んでみて下さいね。
(出展元 : 中海エコ活動レポート)
バックナンバーが読んでみたいと言う方はこちらから
(平成25年12月2日更新)

島田地区中海流出水対策協議主催により、安来市穂日島町にある安来市立島田
小学校において、アマモ植栽イベントを開催しました。天候不良のため11月10日が
28日に、開催場所も島田交流センターから島田小学校に変更して開催しました。
島田小学校5年生の皆さんといっしょにアマモシートを作成することになり、まずは、
島田地区中海流出水対策会の大迫会長が挨拶されました。次に、今回初めて参加
する島田小のみんなに容器に入ったアマモの種子を観察し、種がどんな形か、移植
するアマモシートがヤシから出来ている事、またアマモがどのような役割をもっている
か等を奥森隆夫理事長がわかりやすく説明しました。
島田小のみんなは2班に分かれ、1班さんが教わりながら作ります。アマモの種が入った容器をあけると
独特の臭いにとても驚いた様子でした。ヤシマットの上にみんなで生分解性の不織布を広げ、でんぷん
糊にアマモの種子を混ぜて、シートの上にのせていきます。
前日から各地で初雪の観測されるなか、子供たちが両手を使ってアマモの種を広げていきました。種は
臭いし、糊も冷たくて手が真っ赤になりましたが、最後の1粒まで残さないように丁寧に、そして元気いっぱ
い塗り広げてくれました。もう一枚のヤシマットを重ねたら、協議会の皆さんにバトンタッチ。仕上げの網の
固定は、協議会の皆さんにお願いしました。
2班さんは、1班さんをお手本にどんどん進行していきます。やっぱりヌルヌルした糊が気持ち良いのか?
楽しそうにしていました。最後は、先生もいっしょに種を塗り広げてくれました。もう一枚のヤシマットを重
ねると協議会の皆さんが最後の仕上げを行いました。
2枚を作成し、完成したシートと一緒にみんなで写真を撮りました。
島田小のみんなと別れて、協議会の皆さんがダイバーさんがアマモシートを設置するを見守りました。
時折、雪が降るなかで無事に2枚が設置されました。昨年設置された場所が良く分かるよう、看板が立て
られていました。
寒いなか元気いっぱい参加してくれた島田小学校5年生達、学校の先生方など40名を超える皆さんに
ご参加いただきまして、本当にありがとうございました。
(平成25年11月21日更新)

境港市中野町の鳥取県漁協境港支所において、第9回アマモ移植イベントを開催
しました。小春日和のなか、昨年に引き続き認定NPO法人自然再生センターさん
との共催となりました。
奥森隆夫理事長が、「皆さんの活動により中海の環境が改善されつつあり、アサリ
も増えてきています。今後につなげていきましょう」と挨拶しました。続いて、鳥取県
漁協の景山一夫組合長も挨拶をされ、アマモ移植イベントをスタートさせました。
未来守りチャイルドクラブのみんなを中心にアマモシートを作ります。上級生に教わりながら、アマモの種を
丁寧に塗り広げていきます。何やってもヌルヌルした糊が気持ち良いのか(?)、楽しそうにしていました。
その様子に大人の皆さんも気になって仕方なさそうでした。今回は5枚作成、完成したシートと一緒に写真を
撮りました。
清水港へ移動して、ダイバーさんがアマモシートを設置するを見守りました。子供たちは、ダイバーさんに
声援を送ったり歌を歌ったり、まるで遠足に来ているようでした。
その後、アマモ場再生応援隊の皆さんとダイバーさんは外江港に移動して、こちらでもアマモシートを設置
しました。※設置は、清水港で3枚、外江港で2枚になりました。
最後は「海農駅(うみのえき)」に帰って、中海の海藻肥料で栽培したサツマイモや海藻米のおにぎり、アサ
リのお味噌汁をみんなでいただきました。天候にも恵まれて、中海を満喫した一日となりました。
40名を超える皆さんにご参加いただきまして、本当にありがとうございました。
平成25年11月28日追記 : エコトリピーのブログ「トリピーのTEAS(テス)生活」でも紹介されました。

現在、「ミネラル海藻」の注文が多く入り、製造が間に合わない状態になる可能性があり
お客様のご希望数量にお答え出来ない場合が発生すると思われます。
11月より予約の受付を開始しましたので、早めにご注文を頂けますよう、よろしくお願い
致します。
※お問い合わせフォームか電話・FAXにて、ご連絡をお願いします。
→ お問い合わせへ

平成25年に海藻農法で出来た新米の食味値試験結果が順次出てきました。
導入一年目の皆さんが良い結果を出しています。
→ お知らせへ

日 時 平成25年11月16日(土) AM 9:30 ~PM 12:00
※ 平成25年11月6日追記 : 9日(土)から変更になりました。
受 付 AM 9:00 ~ 9:30
場 所 鳥取県漁協 境港支所(境港市中野町)
アマモシートの設置場所 境港市清水港・外江港
※ 帽子・タオル・傘・長靴などは、各自でご準備お願いします。
※ 雨天の場合、アマモシートの作成のみを行い、設置は中止とします。
共 催 認定NPO法人 自然再生センター
お問い合わせは、事務局まで。

日 時 平成25年11月28日(木) PM 14:00 ~
※ 平成25年11月21日追記 :
天候不良により、10日(日)から変更になりました。
場 所 島田交流センター (島根県安来市穂日島町485)
※ 帽子・タオル・傘・長靴などは、各自でご準備お願いします。
主 催 島田地区中海流出水対策協議会
連絡先 事務局 (島田交流センター)
または、未来守りネットワークまでお問い合わせください。
※6月15日(土)から、変更になりました。
セミナーに関するお問い合わせは、事務局まで。
(平成25年9月28日更新)

境港における海藻の有効活用についてNHKで放送されたことをきっかけに、沖縄県
那覇市にあるコンサルタント会社から海藻農法普及協議会に問合せがありました。
沖縄県では、産学連携として、「ライフスタイルイノベーション創出推進事業」を実施
しています。その研究開発プロジェクトの中で、「漂着海藻を用いた沖縄型マリンオ
ーガニック・ミネラルの開発」が採択されたそうです。
平成25年9月9日・10日に琉球大学准教授をはじめとした5名が、地域課題となっている海藻を肥料に利
活用する先進事例として、中海の視察に訪れました。初日は、まず鳥取県との意見交換会を行いました。
沖縄県での事業化のきっかけはビーチの漂着海藻への対応だそうです。海藻の種類や海藻刈りしたもの
とは違いますが、同様な課題を抱えるもの同士、今後も情報交換していくことになりました。
その後、島根大学の松本真悟准教授を訪ね、中海産海藻肥料の特徴や沖縄の海藻活用法について説明
を受けました。
2日目は、実際に中海での海藻刈りや海藻肥料工場、海藻農法を導入している農家を視察しました。直接
漁業者や農業者から意見を聴いて参考にされているようでした。この様子は、地元新聞の他にテレビでも
放送されましたので、ご覧になられた方もいらっしゃるかと思います。
お忙しい中で多くの方にご協力をいただき、意見交換会や視察を行うこ とが出来ました。また、遠方より
山陰地方へお越しいただき、ありがとうございました。
(平成25年9月27日更新)
 飯梨川河川敷にて「やすぎ環境フェア2013」が開催され、昨年に引き続き、未来守り
飯梨川河川敷にて「やすぎ環境フェア2013」が開催され、昨年に引き続き、未来守りネットワークも水環境への取り組みを紹介したパネル展示と「ミネラル海藻」をPRして
きました。前日までの雨により開催されるのか、心配でした。足元は湿っていました
が奥森隆夫理事長がしっかりPRしてきました。
環境イラスト展示コーナーでは、テーマごとに分けて選ばれた優秀作品が展示され
ていました。日ごろから子供たちが環境に対して熱心に取組んでる様子がうかがい
知れました。国土交通省出雲河川事務所の皆さんと今年も向かい合わせの展示と
なり、一緒に写真を撮ってもらいました。
今年は、新たに島田地区でのアマモ植栽イベントのパネルを加え、未来守りネットワークをより身近に
感じてもらえたら良いなと思います。このような機会をいただきまして、ありがとうございました。
(平成25年8月12日更新)

昨年に続き、中海の海藻採取による浄化活動を学ぶため、地域マネジメントコース
の学生11名が就業体験に訪れました。今回は、韓国からの男子留学生や中国から
女子留学生も参加しました。まずは、奥森理事長から未来守りネットワークの中海に
おける主な活動が説明され、生徒たちはなぜ中海で海藻を採取することが水質浄化
に繋がるのか、メモを取りながら真剣に聴いていました。
海藻農法普及議会の野口理事のブロッコリー畑で、中海産海藻肥料「ミネラル海藻」
などの肥料を施したり、海藻刈りから乾燥などの肥料製造の工程を学んだりしました。
海藻刈りの様子は、山陰中央新報にも取り上げられました。(3段目左の写真は、取材中の様子です)
猛暑の中での慣れない重労働でしたが、無事最後まで全員がやり遂げました。再びこのような機会を与え
て下さった関西国際大学関係者の皆様と地域マネージメントコースの松本茂樹准教授、学生の皆さん本当
にありがとうございました。
毎年7月に開催していましたきれいになった中海で泳がいやですが、今年はクラゲ発生などの事情により
イベント開催を見合わせております。
時期を見て(目安として、8月下旬か9月頃)、アサリの放流などをしたいと考えています。日程が決定しま
したら連絡をいたしますので、よろしくお願い申し上げます。
平成25年12月追記 : 今年度のアサリ放流は、来年度へ延期となりました。
(平成25年7月13日更新)

平成25年7月12日(金)に中部総合事務所で行われた鳥取県希少野生動植物の
保護に関する条例に係る意見交換会に奥森隆夫理事長が参加しました。
→ アルバムへ
(平成25年6月18日更新)
平成25年6月16日(日)に発行された「さかいみなと会議所ニュース」に未来守りネットワークが河川功労者
表彰を受賞した記事が掲載されました。 → さかいみなと会議所ニュースはこちら
(平成25年6月18日更新)

第9回アマモ種子採取イベントの終了後に「海農駅(うみのえき)」に移動し、港湾
工事関係者や行政の皆さんに新井章吾技術顧問が「境水道における生物と環境」
の講演を行いました。
境水道上流部や入り江状の浅場には、十分な酸素を含んだ海水の湧水が豊富で、
トリガイ・サルボウガイ・コナガニシ・ウミサボテン・ウミエラなどが生息し、生物の多
様性が高いことを動画なども活用して説明されました。
そのような事例から、中海・宍道湖の海岸部から集水域における海底での地下海水の湧出環境と降水の
浸透環境の保全と修復により、水質改善が可能と考えられます。海底湧水を増やすための新しい公共土
木事業が漁業振興による活性化のために必要だと思われます。
自然の仕組みを手助けしていくような工事を行っていただけるようお願いして、講演は終了しました。
このような機会を頂戴することができまして、本当にありがとうございました。
(平成25年6月18日更新)

境港市の外江港にて、第9回アマモ種子採取イベントを開催しました。第7回まで、
この時期には完熟したアマモの種子を採集できましたが、昨年も時期が少し遅れ、
の日の外江漁港内のアマモの草長は例年より短く、花枝(かし)が形成されてい
ませんでした。
港外のアマモも栄養株の2%程度の花枝しか確認ができませんでした。そのため、
集まってくれた子供たちには、アサリや巻貝などを観察してもらいました。
この2~3年、アイゴ幼魚の群れがアマモを採食し、晩秋まで草長を短くしていることが原因かもしれません。
アカエイによる地下茎と根の洗掘によってアマモが流出し、藻場がかなり縮小しているため中海のアマモは
危機的状況になっいます。
昨年・今年と2年続けてイベントでの種子採取を行うことが出来ませんでした。あいにく雨の中での開催となり
ましたが40名を超える皆さんにご参加いただきまして、本当にありがとうございました。
(平成25年6月10日更新)

境港市竹内団地の夢みなとタワー第2会議室にて、第9回アマモ・コアマモ勉強会
を開催しました。まず、先月の28日に国土交通省 中国地方整備局長のご推薦
により、未来守りネットワークが平成25年河川功労者表彰を受賞したことについて
奥森隆夫理事長から報告がありました。
次に、奥森隆夫理事長が「安来の承水路を含めた島田地区再生事業」について、
講演しました。安来市島田地区では、平成23年に引き続いて昨年もアマモの植栽
を行っています。そして、2年続けてアマモの発芽が確認されています。
植栽に伴って行われた湖底調査の資料をもとに良い環境の中で、生物多様性が
保たれている現状と今後は、県や市の垣根を越えた中海再生が必要不可欠であると発表しました。
続いて、未来守りネットワークの技術顧問でもある新井章吾氏による「湧水を活用した中海再生」を講演
しました。未来守りネットワークのセミナーや勉強会で、今まで中海の再生には湧水の活用が必要である
と聞いたことのある方もいらっしゃると思います。
自然の栄養塩の循環システムを手助けすることが行政にも求められていると話し、今回は山口県の周防
大島での事例も紹介し、山~川~海へと続いていく栄養塩の循環について雨水が地表から浸透し、また
山の上からの栄養が下の田畑へ、そして最後には海へと繋がっていることを分かりやすく説明されました。
最後の質疑応答では、安来で無農薬栽培に取り組まれている方が、ご自身の畑のそばでも水が湧いて
いて、その湧き水には山の栄養分を含んでいるのではないかと仰られ、栄養塩の循環を実感されている
ようでした。安来市島田地区からも2年続けて勉強会にご参加をいただいています。
お忙しい中、お越しくださった皆さま、本当にありがとうございました。
(平成25年5月31日更新)
 国土交通省中国地方整備局長よりご推薦をいただき、公益社団法人 日本河川
国土交通省中国地方整備局長よりご推薦をいただき、公益社団法人 日本河川協会より、平成25年河川功労者として、未来守りネットワークが表彰されることに
なりました。
東京都にある砂防会館別館シェーンバッハ・サボーにて、日本河川協会の総会前
に行われた表彰式に奥森隆夫理事長が出席しました。
平成25年河川功労者表彰は、個人42名および44団体が受賞しました。
未来守りネッワークは、第4項河川の自然保護・環境学習・河川愛護等の活動に
功績があったとして選ばれました。平成16年に設立以来、水質汚染や中海干拓事業により激減したアマモ
・コアマモ場の復活に取り組み、「アマモの移植イベント」等を実施して、中海沿いの住民の河川愛護活動を
先導し、環境保全に対する意識向上に尽力されたと功績を認められました。
皆様から、たくさんのお力添えをいただいて、このような賞を受賞することができました。
ありがとうございました。
(平成25年5月31日更新)
 南部町にある「とっとり花回廊」を中心に天皇皇后両陛下をお迎えして、「感じよう
南部町にある「とっとり花回廊」を中心に天皇皇后両陛下をお迎えして、「感じよう森の恵みと 緑の豊かさ」をテーマに掲げ、第64回全国植樹祭が開催されました。
式典では、天皇皇后両陛下によるお手植え・お手播きが行われ、子供たちと苗を
植えたり、種をまかれました。子供たちにも笑顔でお声をかけられ、手を真っ黒にし
植えられる姿が印象的でした。
未来守りネットワークからは、奥森隆夫理事長が記念式典に参加してきました。
足立統一郎顧問も式典に参加され、式典の後はみんなで植樹会場へ移動し、苗木
の植樹を行いました。当日は暑いくらいの好天に恵まれてまさに森の恵と緑の豊かさを感じた一日となり
ました。

日 時 平成25年6月8日(土) AM 10:00 ~PM 12:00
場 所 夢みなとタワー 2階 第2会議室
演 題 1.「安来の承水路を含めた島田地区再生事業」
NPO法人未来守りネットワーク 理事長 奥森隆夫
2.「湧水を活用した中海再生」
㈱ 海 藻 研 究 所 所 長 新井章吾 氏
※6月15日(土)から、変更になりました。
セミナーに関するお問い合わせは、事務局まで。

日 時 平成25年6月15日(土) AM 9:30 (受付)~PM 12:00
集合場所 採取場所 外江港
※ 雨天決行します。
※ カッパ・手袋・タオル・傘・着替え等は、各自でご準備願います。
※ 一部会員は、AM 8:00 に集合
※ 6月8日(土)から、変更になりました。
イベントに関するお問い合わせは、事務局まで。
(平成25年5月2日更新)
海藻農法普及協議会のホームページで、既にお知らせをしていますが、サーバーの大規模なシステム
チェックが行われます。これに伴い、サーバーが一時停止します。また、翌日の午前中にかけて繋がり
にくい状況が続きますので、ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いします。
サーバー停止時間 : 平成25年5月2日 am 10 : 00 ~ pm 22 : 00
※未来守りネットワークは、別のサーバーを使用しています。
お急ぎの場合は、未来守りネットワークまでご連絡をお願いします。
(平成25年3月18日更新)

海藻農法普及協議会が3月16日・17日の2日間に野菜市を行いました。
観光シーズン到来に合わせて、テントを張っての開催となりました。2日間とも天候
に恵まれ、暖かい春の日差しの中での野菜市でした。春の訪れとともに田畑の準
備にと肥料をお求めになられるお客様が多かったように思われます。
観光に水木しげるロード等を訪れたお客様が野菜が安いと購入され、お土産にと
シジミを使った海産物もとても人気がありました。
お越しくださった皆さま、本当にありがとうございました。
この様子は、海藻農法普及協議会のホームページでもご覧いただけます。 → こちらから

日 時 平成25年3月16日(土)・17日(日)
AM 10:00 ~PM 3:00
場 所 元気亭。よこ(海農駅) 鳥取県境港市大正町38番地
※ ミネラル海藻(350g入り)をイベント期間中は、900円で販売します。
※ カフェコーナーでは、地元境港の「福浦」のお菓子とドリンクのセット
もございます。
※ 境港の海産物の販売も予定しています。
主催 海藻農法普及協議会
野菜市のチラシは → 野菜市開催のご案内
海藻農法普及協議会のホームページでも紹介しています!
(平成25年2月27日更新)

海藻農法普及協議会が2月23日・24日の2日間に野菜市を行いました。“海の駅”
の店頭や店舗の中での開催でした。2月も終わりとはいえ雪の予報に天候も心配
されましたが、時折雪がちらつく程度で、積もることもなくすみました。チラシを見た
と「ミネラル海藻」を朝早くからお買い求めになるお客様がいらっしゃいました。
日野町から水稲への利用をご検討中というお客様が来店され、現在は兼業農家
だけれど将来、専業になるまでに付加価値のついた美味しいお米作りを模索して
おられたそうです。
ちょうど海藻を施肥することを話題にしていた時にたまたまチラシが目に入ったそうで、良い機会だから
と話を聴きにこられました。
ほかにも家庭用菜園用の小袋を以前購入され、ご自身で大根などを作って結果が良かったと言われる
地元の境港の方が再度購入されました。海の駅で購入したジャガイモがとても美味しかったと仰っていた
だきました。実際に使った結果を報告してくださり、またリピーターとして来店していただき本当に嬉しく思
います。
寒い中をお越しくださった皆様、本当にありがとうございました。
この様子は、海藻農法普及協議会のホームページでもご覧いただけます。 → こちらから
(平成25年2月26日更新)

海藻農法普及協議会が境港市の夢みなとタワーにおいて、「第2回 中海産海藻
肥料による農業改革セミナー ~中海の現状と農業再生~」を開催しました。
最初に金澤会長が挨拶をし、新井章吾技術顧問がまず「中海の現状」について
講演しました。海中写真を使用し、中海の海藻を採取するに至った経緯を説明
するとともに国内外の各地で同様に海藻を肥料として利用している事例も紹介さ
れました。
中海で広範囲に湧いている湧水の活用や季節的要因を考慮した取り組みが漁業 振興に繋がること
を 発表しました。
中海の現状を学んだ後、島根大学 生物資源科学部 附属生物教育研究センター 准教授 松本真悟氏
による「中海産海藻肥料による農業改革」の講演が行われました。松本准教授には、以前より肥料化
に向け、ご相談させていただいていました。
肥料は鉱物資源から作られているそうですが、日本ではこの鉱物資源が生産されないため、肥料の
自給率はゼロでリンとカリについては輸入に頼らざるを得なくなっています。価格高騰に伴い循環型
農業に移行することが求められています。
中海で採取される海藻にカリが多く含まれていることも説明され、古くから利用されていたように農業用
資材としての活用が再考されます。
講演後には、質疑応答が行われました。中でも静岡県から参加されたはまなこ環境ネットワークさんも
質問され松本准教授がわかりやすく説明されました。浜名湖ではアマモが繁殖し、漂着したアマモを回収
して肥料として活用する取り組みを行っているそうです。
最後に奥森隆夫理事長が副会長として挨拶をし、海藻成分を多く含んだ画期的なペレット肥料が完成
した事も発表しました。たくさんの皆さんにご参加いただきまして、ありがとうございました。
海藻農法普及協議会のホームページでも紹介しています。 → こちらから
海藻農法普及協議会がミネラル海藻で育てた海藻米を中心とし通販サイトをオープンました。
海藻農法OnlineShopのサイトへ
海藻農法普及協議会のホームページからもサイトへ入れます。
日 時 平成25年2月22日(金)13:30~15:10
会 場 夢みなとタワー2F 第3会議室(境港市竹内団地255-3)
内 容 13:30 開会挨拶
海藻農法普及協議会 会長 金澤啓造
13:40 「中海の現状」
㈱海藻研究所 所長 新井章吾
14:10 「中海産海藻肥料による農業改革」
講 師 松本 真悟
14:50 閉会挨拶
海藻農法普及協議会 副会長 奥森隆夫
主 催 海藻農法普及協議会
協 力 NPO法人未来守りネットワーク
お申込は、協議会ホームページから

日 時 平成25年2月23日(土)・24日(日)
AM 10:00 ~PM 3:00
場 所 元気亭。よこ(海農駅) 鳥取県境港市大正町38番地
※ ミネラル海藻(350g入り)をイベント期間中は、900円で販売します。
※ カフェコーナーでは、地元境港の「福浦」のお菓子とドリンクのセット
もございます。
※ 境港の海産物の販売も予定しています。
主催 海藻農法普及協議会
野菜市のチラシは → 野菜市開催のご案内
海藻農法普及協議会のホームページでも紹介しています!
(平成25年1月29日更新)

県庁内にある島根県職員会館 多目的ホールにて、第9回 第3期中海自然再生
協議会が開催されました。未来守りネットワークからは、奥森隆夫理事長が出席
して、昨年11月に自然再生センターさんと共催した「アマモ・コアマモ再生イベント
(よみがえれ中海)」 について報告を行いました。
アカエイがアサリ幼貝を捕食する際、ヒレで砂を洗掘することによる被害について
も報告し、アマモシートに用いる金網がアカエイによる被害の軽減に有効であること
を伝えました。
(平成25年1月28日更新)

平成25年1月22日にホテルニューオータニ佐賀にて「第9回 九州・沖縄ブロック
地方議員フォーラム in 佐賀」が開催されました。“地域資源「なかうみ」海藻肥料
を活用した6次産業化へのチャレンジ”と題し、奥森隆夫理事長が講演を行いました。
また、新井章吾技術顧問は、その背景としての「海藻肥料と海底湧水による農地と
海の地質循環~物質循環の修復による一次産業の再生~」について講演しました。
一昨年にミネラル海藻のPRのために訪れた佐賀県で佐賀市議会議員をされている千綿氏から、お声を
かけて頂き、この機会を得ることが出来ました。九州・沖縄地方の議員の皆さんに地域資源を活用した
取組みについてとても良いPRになったと思われます。
当日は60名もの皆さんが熱心に話を聴いて下さり、本当にありがとうございました。
この様子は、海藻農法普及協議会のホームページでもご覧いただけます。 → こちらから
(平成25年1月28日更新)

和鋼博物館(安来市安来町) 映像ホールにて、中海漁業の振興を考える会主催に
より、「豊穣の中海 再生をめざして」と題しシンポジュームが開催されました。
未来守りネットワークからは、新井章吾技術顧問が出席して、水質・資源調査結果
を報告しました。
調査箇所は、飯梨川河口付近のほか、国交省が浅場造成工事を行った安来市
汐手ヶ丘地先、松江市東出雲町意東地先の3箇所で、それぞれ2枚貝や湧水量、
水質について調査を行いました。
調査を終えて、中海の漁業資源の復活には定点を設けた定量調査ではなく、浅場の面的な調査による
定性的な環境と生物の分布を把握する必要性を感じました。定期的かつ継続した調査によって、共有
できる客観的データを蓄積していくことが重要です。
また、地下湧水活用のため地形や潮流などの要因に基づいた技術的手法の改善、季節的要因を考慮
したアサリ幼貝の移植や畜養への活用などといった一年を通した資源保護が有効だと考えられます。
調査報告の後には、パネルディスカッションが行われました。パネリストとして一般市民や民間研究者に
加えて、漁業者や島根県水産技術センター、国土交通省中国地方整備局出雲河川事務所といった様々
な立場の方を迎えた意見交換が行われました。
本日より25年度がスタートします。本年もよろしくお願いします。